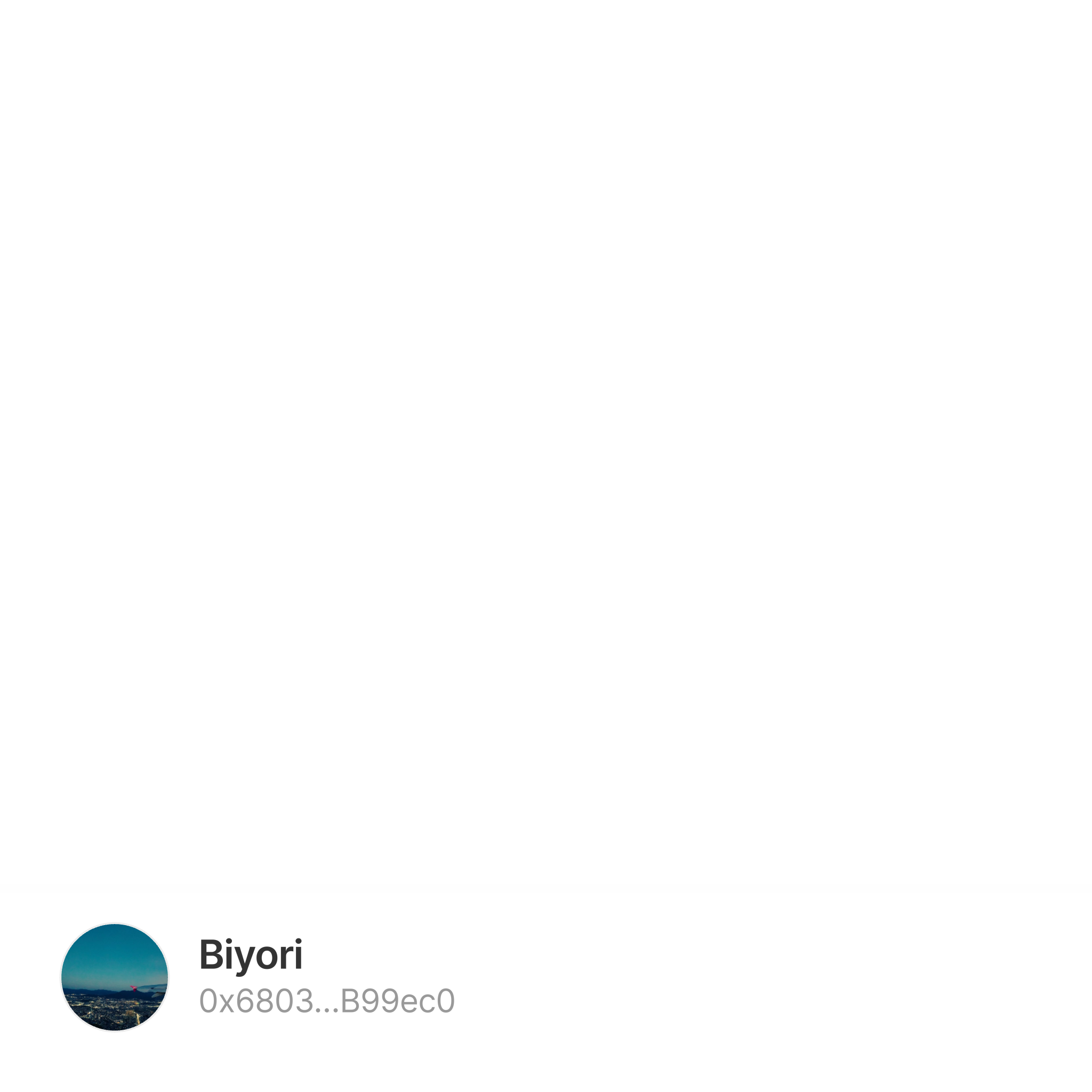電子音楽とゲーム音楽
音楽といえば基本的には「Shape of you」や「Despacito」、「MEAN!」などのメジャーアーティストが手掛けるものを想像するかもしれない。しかし、こと21世紀においてはロックやパンク、フォークなどと同様に電子音楽が注目されている。例えばEDMはマシュメロやアランウォーカーを筆頭に天文学的なクリエイターによってその地平が切り開かれ、LoFiやチルウェーブ、ファンク、ヒップホップなどが進化の系譜を紡いだ。
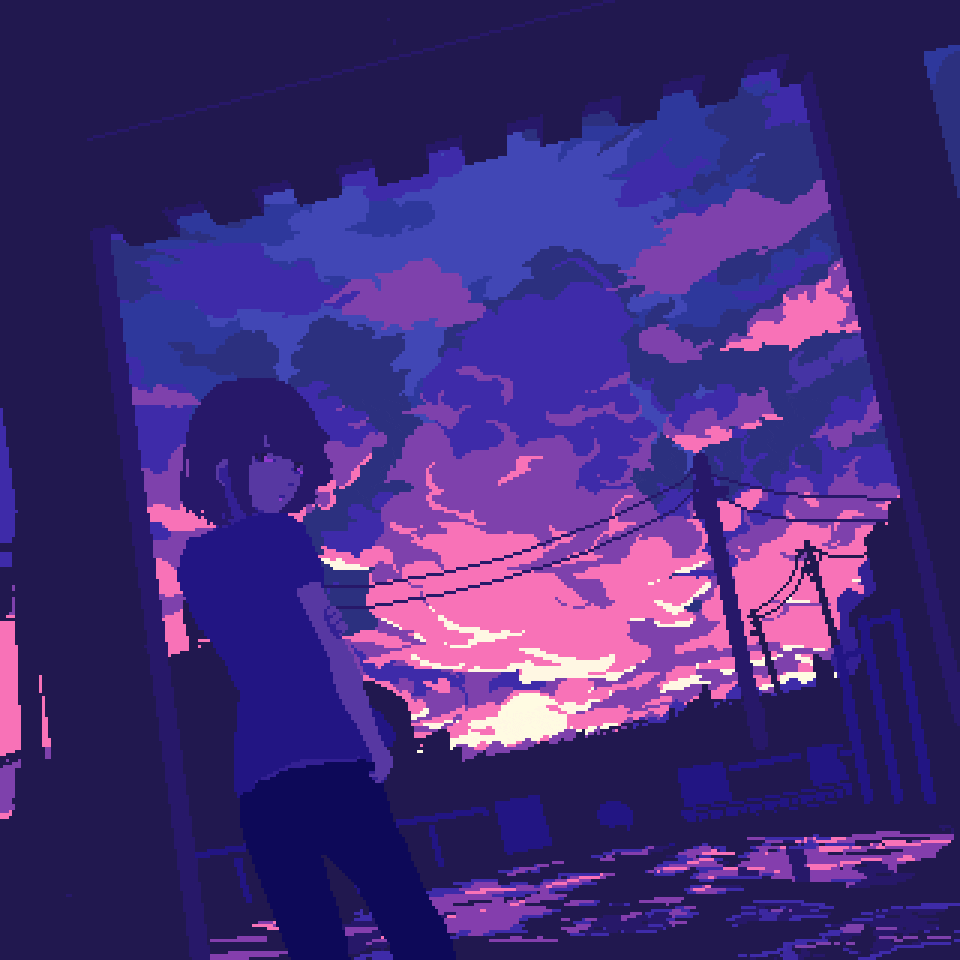
しかし、電子音楽という言葉をウィキペディアで調べると、少し頭をかしげる現象が起きる。そう、それは第二次世界大戦のころから存在するもので、2010年代の音楽を名指しするものではない。電子音楽というとなんだか現代っぽく、最近っぽいイメージを抱きがちだが、その実態は化石同然、かなりクラシックなものとしてとらえられるほどに歴史が深い。
インストとローファイ
では、最近よく耳にしているあの音楽は何か。例えばシヴィライゼーション6のメニュー音楽であったり、Mihoyoのタイトルのゲーム内音楽であったり、FFのサントラ、あのボス戦の曲、あのモンスターとの戦っているさなかに延々と流れている終わりのないあのゲーム音楽は、電子音楽ではなければ何なんだろうか。
インストヒップホップやLoFiヒップホップはR&Bやレゲエ、ロックぽい味を出しておきながら、延々と流れていても不思議ではないというふわふわした感触を受ける。LoFiならばことさらだが、数年前にはやったYoutube上でのLoFi音楽垂れ流し配信「LoFi Girl」がまさにそれで、LoFiヒップホップを体現していたといってもいいだろう。
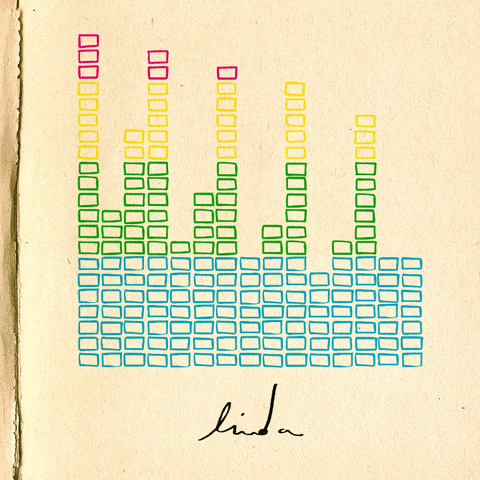
そして、インストヒップホップなどの作業用音楽的音楽とは別のストリームとして、ゲームとしてのインストヒップホップがあるように思える。
しかし、ゲームとしてのインストヒップホップは存在するわけではなく、正確にはゲーム内音楽に従来の音楽が含まれているといったほうが正鵠を得ている。そして、上記のなんとかヒップホップも、ゲームらしさを付け加えているといったほうがいいかもしれない。つまり、それぞれの立場から別の立場を標榜しているということである。
2つの立場

ゲームはミュージックを見つめ、ミュージックはゲームを見つめている。
アメリカントラックシミュレーターやグランドセフトオートなどでは、ラジオ音楽としてマルーンVやジャスティンビーバーなどを聴くことができる。しかも、ゲームによっては1年以内にリリースされた有名アーティストの音楽を取り込んでいるものもあり、ゲーム内音楽は「普通に音楽でいい」ことがうかがえる。
非ゲーム音楽、つまりは通常の音楽でありEDMでありラッパーが作った曲であり、音楽としての音楽は、ゲーム音楽という概念を投影するときに音楽の「音でありリズム」の部分にフォーカスをしてアプローチしている。しかし、ゲーム音楽が非ゲーム音楽に対して抱いている感情は真逆で、「メロディーであり旋律」を主要なアプローチポイントとしている。
従って、ゲームをやっているゲーム内空間でカリードやドレークの音楽を聴くという状態がAであるとすると、車を運転しているときにLoFiヒップホップを聴くという状態がAに匹敵する。
それぞれは別の世界「リアル」と「バーチャル」からのアプローチではあるが、求める完成物のイメージは同じである気がしてならない。