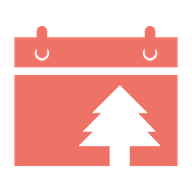要約
○ CC0は、NFTアートプロジェクトを盛り上げることに一役買っている
○ しかし、CC0は、2次創作の著作権をコントロールできない弱点を抱えている
○ この問題は、コピーレフトを盛り込んだライセンスを採用することで解決可能だ
NFTアートプロジェクトで注目されるCC0
CC0を採用したNFTアートが注目されています。
CC0とは、著作権等を放棄し、著作物を誰でも自由に利用できる状態にすることです。 例えば、CC0が採用されたアートは、二次創作のNFTアートをMintしたり、マグカップにプリントして売ったりすることができます。
CC0 とは、科学者や教育関係者、アーティスト、その他の著作権保護コンテンツの作者・所有者が、著作権による利益を放棄し、作品を完全にパブリック・ドメインに置くことを可能にするものです。CC0によって、他の人たちは、著作権による制限を受けないで、自由に、作品に機能を追加し、拡張し、再利用することができるようになります。
CC0は、著名NFTプロジェクト「Nouns」がこれを採用したことで注目されています。 Nounsは、下記「Noun117」のようなかわいいピクセルアートNFTを1日に1つ、自動生成・発行するプロジェクトです。
Nounsの例において、CC0を採用する最大のメリットは、「みんなが勝手にNounsを盛り上げてくれること」です。 Nounsでは、ピクセルアートを元にした3Dボクセルアートを作る「3DNouns」やファーストフード版のNounsを作る「Fast Food Nouns」といったような派生プロジェクトが生まれて盛り上がっています。 「Nounsは誰のものでもない」という状態を作ることで、Nounsを中心としたコミュニティ全体が盛り上がっているように見えます。
CC0の弱点
私は、CC0には以下のような弱点があると考察しています。特に、日本のNFTアートシーンでは、その弱点が顕著になると考えられます。
CC0の弱点は、2次的著作物の著作権を制限できないことです。
CC0として公表された著作物について、2次創作が行われたが、その2次創作の著作権が保持されたままの場合、CC0のバトンはそこで断たれてしまいます。その2次創作についてさらに2次創作をすることはできなくなります。
例えば、
① Aさんが、2DキャラクターSのアートをCC0で公表する
② Bさんが、キャラクターSのボクセルアートS2を著作権を保持したまま公表する
③ Cさんが、ボクセルアートS2をモチーフにしたアート作品S3を作成し、公表する
この場合、③の行為は著作権侵害を構成する可能性があります。②でBさんが行った創作には、2Dアートの3Dへの描き起こしというBさん独自の創作性が発揮されており、その新たに加えられた部分についてはBさんが独自の著作権を有するためです。

なぜ弱点なのか
NFTアートプロジェクトへのCC0の採用を検討されている方の多くは、ファンアートのような2次創作が活発に行われることで、プロジェクトのブランディングやマーケティングに良い影響をもたらすことを期待していると思います。
先のNounsの例もそうですが、日本においても、少し前では東方Projectや初音ミク、最近ではVTuberのファンアート文化など、中心となるコンテンツを二次創作が盛り上げ、その知名度やブランド価値を向上させるというカルチャーが随所で見られます。
さらに、NFTアートでは、プロジェクトをDAOとして運営することによって、中心コンテンツの価値上昇分をコミュニティ全体に還元することができます。例えば、コンテンツを盛り上げてくれた人にガバナンストークンを譲渡する、あるいは、元から保持していたガバナンストークンの価値にコンテンツの価値上昇が反映されるなどして、適切なインセンティブを付与することができます。
このような中心コンテンツとコミュニティの盛り上がりという観点からすると、CC0は以下のような弱点があります。
第一に、2次創作の幅を狭めることです。
先の例②のように、第三者(Bさん)がボクセルアートを作成しその著作権を保持したままの場合、別の第三者(例えばDさん)がBさんの作品とは別のボクセルアートの制作をしようとすると、当該行為はBさんの著作権侵害となる可能性があります。仮に、本当は著作権侵害にあたらない場合であっても、Dさんが侵害となることを恐れて創作を躊躇する、という萎縮効果があります。
自らの著作権を主張する2次創作者が現れると(このような主張自体は正当で尊重されるべきだが)、その人の表現手法の限りで、中心コンテンツの2次創作の幅は実質的に狭まってしまいます。
第二に、互いに2次創作しあう関係性の構築が阻害されることです。
先述の通り、NFTアートプロジェクトでは、コミュニティの盛り上がりが重視されます。
2次創作の連続が断たれてしまうコミュニティよりも、2次創作が広がっていく、あるいは、相互に2次創作しあうコミュニティの方が、盛り上がりという点で優位だと考えられます。
自らの著作権を主張する2次創作者が現れると(このような主張自体は正当で尊重されるべきだが)、その時点で2次創作による関係構築の連鎖が断たれてしまい、コミュニティの盛り上がりという観点では不利になります。
【解決策】コピーレフトを採用したライセンス
先のような弱点を克服するためのアイディアとして、コピーレフト(Copyleft)を採用したライセンスを用いることが考えられます。
コピーレフトとは、「著作物を自由に使っていい代わりに、2次的著作物もみんなに自由に使わせてあげてね。」という考え方です。ここでは、著作権を放棄するのではなく、著作権を保持したまま、権利者が指定した目的・方法の限りで著作物を使用する限りは著作権を行使しない意思を表示しています。
コピーレフトを採用したライセンスとしては、例えば、OSS(オープンソースソフトウェア)のライセンスの代表例の1つである「GPLライセンス」が挙げられます。GPLライセンスが付されたソフトウェアは、プログラムの実行、改変、複製物の再頒布などが無償かつ自由である一方で、派生して生まれた著作物には GPLライセンスを適用することが強制されます。
アート関連のライセンスでは、「CC BY-SA」がコピーレフトの発想を実現しています。自らの作品にCC BY-SAを付すと、これについて2次創作を行った者に対して、元の作品と同じライセンス(=CC BY-SA)の下に頒布することを要求できます。その他、CCライセンスは様々なバリエーションを用意しているので、調べてみると面白いです。
上記のような、コピーレフト的思想を取り入れたライセンスを用いれば、自由に2次創作できるかわりに、その2次創作についてさらに2次創作を許すように著作権を一定程度制限することができます。このようなライセンスを付して著作物を公表することで、真に自由な2次創作ができるコミュニティを作ることができると考えられます。
なければ作ろうWeb3時代のライセンス
上記で、紹介したGPLやCC BY-SAといったライセンスはほんの一例です。
重要なのは、あなたは、あなたが思い描く理想の作品の使われ方に合致したライセンスを選ぶべきだということです。この点、コピーレフトは、「作品を中心に置いてコミュニティが盛り上がる」というゴールに対しては有効であると考えられます。
さらに踏み込んで言えば、既存のライセンスで適切なものが見つからないなら、新しいライセンスを策定することを含めて検討すべきです。
NFTの技術は、アーティストがその作品に見合った価値を受け取る方法を提供しました。それはこれまでの人類史になかった方法であり、どのライセンスもNFTによる収益化を予定していません。
そこで、私は、NFT発明以降の、Web3の時代に適合した新しいライセンスを策定したいと考えています。
ひとまず、この記事に包含される画像を含めた著作物については、下記のライセンスを付して、結びとさせていただきます。
- 継承;もしあなたがこの記事をリミックスしたり、改変したり、加工した場合には、あなたはあなたの貢献部分をこの記事と同じライセンスの下に、また、そのことを明示して、頒布等を行ってください。
- 以上の条件に従う限り、あなたは、いかなる媒体・方法でも、この記事の複製・再配布・翻案を自由に行うことができます。
- 私は、このライセンスの条件を変更することがありますが、当該変更は将来に向かってのみ効力を及ぼし、既に頒布等を行った第三者の利益を害しません。
この記事は、あくあたん工房Advent Calendar 2021、8日目の記事でした。