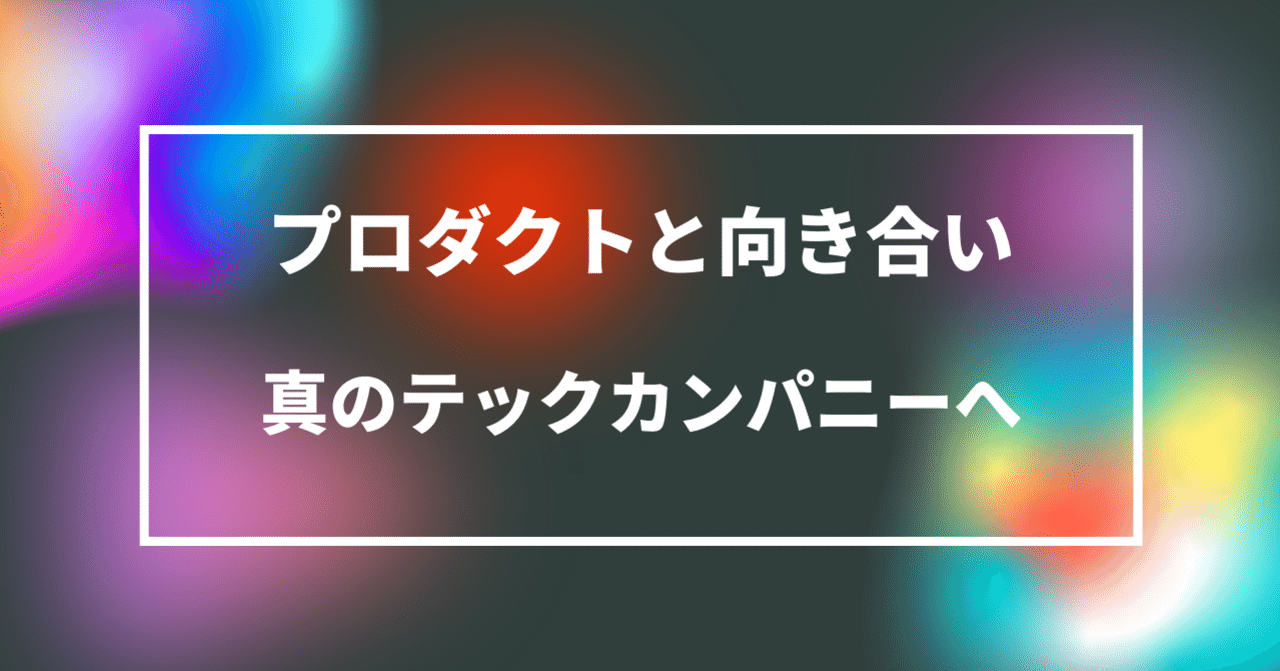皆様、新年あけましておめでとうございます。
前職のトリドールホールディングスから、現職のakippaにジョインして、ちょうど1年半が経った。トリドールは丸亀製麵などの飲食チェーンを運営する外食企業で、akippaはC to Cの駐車場オンライン予約サービスを運営するIT企業。もちろん“IT”と“飲食”とで違う点は多いんだけれども、akippaの経営に携わったこの1年半の中で、「結構、“IT”と“飲食”って似てるんじゃないか?」と思うこともあり、また正月休みで時間もあったので、なぜ「ITと飲食が似ている」と思うかを整理してみた。
素晴らしい“体験”を提供できるかどうかが大事
When this experience delta is great enough, it creates “wow” moments for new users. “Wow” moments lead to word-of-mouth viral growth and high net promoter scores.
― Bill Gurley
BechmarkのBill Gurley氏は「デジタルマーケットプレイスを評価する際に考慮すべき10の要素(10 Factors To Consider When Evaluating Digital Marketplaces)」という文章の中で、新しい体験と既存の体験のデルタ(変化量)が十分に大きいかどうかが重要と指摘している。この体験のデルタが十分に大きいと、ユーザーにとって「ワオ」という瞬間が生まれ、口コミによるバイラルな成長と高いNPSにつながる。
香川県丸亀市を訪れた時、小さな製麺所の前に長蛇の列ができているのを見て、ものすごいショックを受けました。建物、サービスはごく普通ですが、目の前でうどんが作られ、できたてを食べられることに多くの人が引きつけられている。どうすれば集客できるかをずっと考えてきた中で、一つの答えを見つけた気がしました。
― 粟田 貴也
丸亀製麵は店内でうどんを手づくりしている。全国に800以上の店舗が存在するが、例外はない。飲食チェーンはセントラルキッチンを設置し、そこで半製品にまで加工して、最後店舗で加熱や盛り付けをして提供することが一般的である。その方が料理のクオリティも安定するし、店内のオペレーション負荷が少ない。しかし、丸亀製麵では「目の前でうどんが作られ、できたてを食べられる」という顧客の体験を、より重要視している。まさにセントラルキッチンで作られた料理が、店舗で温め直されただけの既存の体験と、目の前で調理され、できたてのうどんを食べられる新たな体験を比べた場合に、そのデルタが十分に大きく、ユーザーに「ワオ」の瞬間を生んでいる事例である。
結局はデジタルであるオンラインの体験であれ、店舗というオフラインの体験であれ、ユーザーが驚くほどの満足を得られる体験を提供できているかが、ユーザーのリテンションに直結するのである。
ユニットエコノミクスが成立するかどうかが大事
ユニットエコノミクスとは、単位あたり採算性を表す指標であり、一般的にSaaSでは「1顧客あたりの採算性(経済性)」を示す指標として用いられている。ユニットエコノミクスを論じるときに頻出するのが「LTV vs CAC」と「Payback Period」の2つの観点だと思う。
LTV(Life Time Value:生涯顧客価値)とCAC(Customer Acquisition Cost:顧客獲得単価)の2つの概念を用います。LTVは「1顧客が生涯に渡ってもたらす利益」を表し、CACは「1顧客を獲得するのにかかる費用」を意味します。LTVがCACの3倍以上だと良いと言われています。
― 大久保 洸平
飲食では、「FLR比率」という考え方が浸透している。Fは「Food」で原材料費、Lは「Labor」で正社員やアルバイトの人件費、Rは「Rent」で店舗の地代家賃のこと。一般的に売上に対する理想の「FLR比率」は70%以下が基準と言われている。その中でも「FL比率」は60%以下が理想だと言われており、家賃は10%以下に抑えるのが通常(もちろん様々な例外はある)。
「LTV vs CAC」も「FLR比率」も、結局は、ユニットあたりでどれくらい利益が残るかを言っている。飲食の採算性を考えるにあたり、最小のユニットは“店舗”だ。店舗あたりで「FLR比率」が70%に以下に抑えられると、それ以外の費用が10%くらいだとすると、店舗段階の営業利益で20%くらいは残せる。そうすると、本部コストで5%を控除したとしても、全社としては15%くらいの営業利益で安定的にスケールできるのである。
LTV/CAC比率が3ってのはどこから来てるの?ってよく見る気がする。特に調べずに原理原則の僕の理解をメモ。TV/CACは要するに、ストック売上に対する、広告宣伝費や営業人件費の比率が33%になるということ。でそれ以外のコストで原価や顧客維持に関わるコストやバックオフィスのコストなどで20-40%くらいコストがのる。ので営業利益率でいうと30-50%目指すにはそれくらいのエコノミクスが必要ってだけかなと。
― 福島良典
一方、SaaSなどでよく使われる「LTV vs CAC」について、Layer Xの福島さんが、自身のTwitterで、なぜLTVがCACの3倍以上だと良いのかを説明していた。結局、ユニットエコノミクスを成立させることがゴールではなく、スケールするためにCACの3倍のLTVが必要なのである。
丸亀製麵では年間に100店舗以上をオープンしていた(3日に1店舗のペース)時期もあるけど、ユニットエコノミクスが成立していたから積極的な投資ができた。IT企業でも「LTV vs CAC」や「Payback Period」というユニットエコノミクスが成立していれば、営業人材を採用したり、広告宣伝費をかけたりして、一気にスケールできる可能性が出てくる。
同じ目標に向かって協力できる組織が大事
IT企業のよくある事象として、「エンジニア vs セールス」がある。エンジニアからすると営業は「急な案件を無茶ぶりしてきたり、突然要件を変えてくる」人たちであり、営業からするとエンジニアは「要件を伝えてもできないと言われる、動きが遅い」人たちと捉えがち。根本的には、お互いの職務内容や利害関係の理解不足から生じる問題である。
飲食でも同様に「商品開発 vs 店舗営業」という利害関係が発生する。商品が売れない理由を、商品開発は営業に求めがちであり、営業は逆に商品開発に求めてしまう。特に100店舗以上ある大型チェーンでは、単に“美味しい商品”を開発するだけでは足りず、店舗でのオペレーションも考慮して再現可能性のあるレシピにしないといけないし、原材料の調達コストや物流の問題も考えないといけない。その中でヒット商品が生まれる瞬間は、顧客が真に求めるものに対して、部門を超えて組織が協力できているときだった。

エンジニアや商品開発の人たちは、新しい技術が好きだし、モノを創り出すことに集中する。営業はIT、飲食問わず、目の前の顧客とのコミュニケーションが好きで、数字へのコミットが強い。エンジニアも営業もアプローチが少し異なるだけで、顧客に対して驚くほどの満足を得られる体験を提供するという共通の目標は変わらない。多様なメンバー間のコラボレーションを生み出すためには、それぞれの長所や得意なことを素直に認め合い、相互に尊敬できるような組織文化を作っていくことが、組織に所属する全員に求められる。
プロダクトと向き合い、真のテックカンパニーへ
弊社のCEOは、よくラーメン屋の例えを使う。単に“ラーメン好き”だからではなく、やはり“ITと飲食は似ている”からだと思う(たぶん・・・)。
「ラーメン屋で新規のお客さんが来て、その人にもう一度来てもらうことはとても大変。味を磨かず微妙なまま店舗拡大するとどうなるか?」社外取締役の原田明典さん(DeNA)はよくそんなことをおっしゃられます。akippaの場合はどうか? ラーメン屋でいう「新規出店」「新規集客」には注力できている。でももう一度来てもらうためにプロダクトの「麺」や「スープ」を良くすることに全社をあげて取り組めてはいない。これが現状です。
― 金谷元気
2022年はプロダクトに向き合い、少しでも“真のテックカンパニー”に近づけたらと思います。そして、「“なくてはならぬ”をつくる」というミッションの実現に向けて、CEOを全力で支援して参ります。2022年が皆様にとっても、明るく希望に溢れる1年となりますように。今年も変わらぬご指導のほど、よろしくお願い申し上げます。